お金を整える|赤字家計から抜け出すための“土台づくり”ガイド
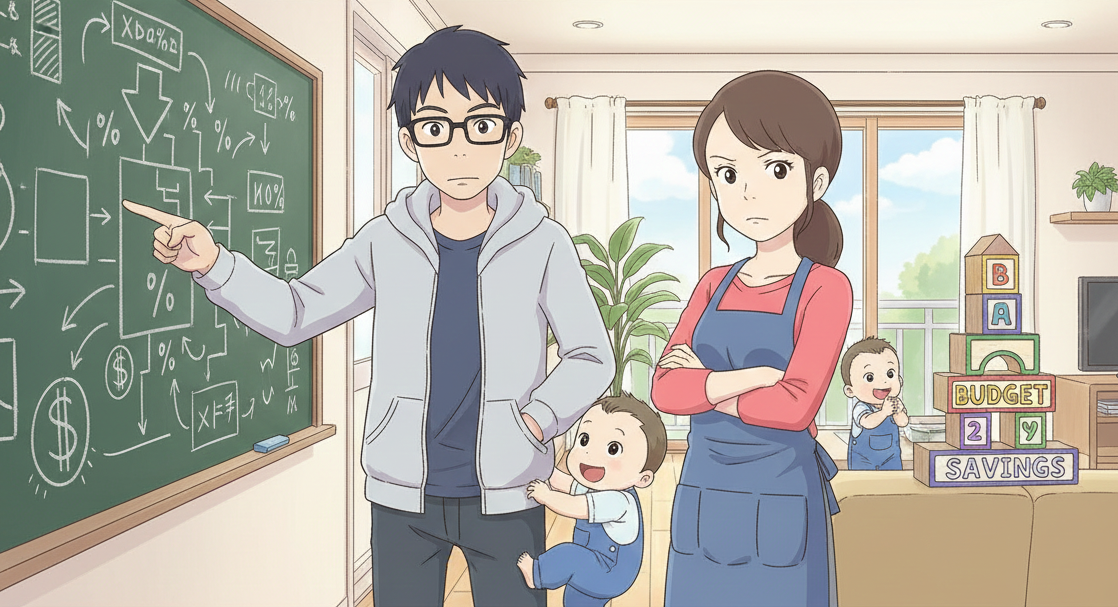
毎月なんとかやりくりはしているけれど、「このままで大丈夫かな…」と感じていませんか?
「お金を整える」では、まずは家計の土台を整えて、赤字や不安定さから抜け出すためのヒントをまとめています。
この「お金を整える」で分かること
- 毎月の収支をざっくり把握するシンプルな方法
- 固定費(通信費・保険・サブスクなど)をムリなく下げるコツ
- 赤字が続くときに、最初に見直すべきポイント
- 家計簿が続かない人向けの「ゆる家計管理」の考え方
- ボーナスや臨時収入に振り回されないためのルール作り
はじめに読んでほしい記事
「何から手をつければいいか分からない」という方は、まずこちらの記事から読むのがおすすめです。
家計を3つの箱に分けて考える|赤字家計を抜け出すための“全体像”のつかみ方
まずは家計の全体像を「3つの箱(消費・浪費・投資)」に分けて整理。何にどれだけ使っているのか、ざっくり把握するところから始めます。
固定費の見直し完全ガイド|通信費・保険・サブスクをムリなくスリムに
いきなり食費を削るのではなく、まずは効果の大きい「固定費」から。見直しの手順とチェックポイントをまとめました。
家計簿が続かない人へ|ざっくり管理でOKなゆる家計術
「きっちり家計簿」は続かなくて当たり前。ざっくり把握でも十分うまくいく、ゆるい管理方法を紹介します。
お悩み別ガイド
今のあなたの状況に近いものを選ぶと、読むべき記事が絞りやすくなります。
📉 毎月ギリギリで貯金どころじゃない
- まずは赤字家計から抜け出すための3ステップ
- 「どんぶり勘定」から抜けるためのゆる家計簿の付け方
- ボーナスに頼らない家計の組み立て方
💸 保険料やローンが重く感じる
- 入りすぎていない?生命保険・医療保険の整理術
- 住宅ローン以外のローンとどう付き合うか
- 借金があるときの優先順位のつけ方(貯金・返済・投資)
📱 通信費・サブスクを整理したい
- 格安SIM・光回線の見直しチェックリスト
- サブスクの棚卸しと「残す/やめる」の判断基準
- 子どもの習い事・サービスにかけすぎていないか見直す
テーマ別の記事一覧
家計の見直し
- 家計の全体像をつかむ方法
- 項目別の予算の決め方
- 共働き世帯の家計管理の分担アイデア
固定費削減
- 通信費の見直しポイント
- 電気・ガス料金のプラン比較
- サブスクサービスの整理術
保険の整理
- 保険証券の「見える化」のやり方
- 子育て世帯に必要な保障・不要な保障
- 学資保険をどう考えるか
よくある質問
Q. 赤字家計のままでも投資を始めていいですか?
基本的には、まず「お金を整える」ことが優先です。
毎月の生活費が足りていない状態で無理に投資をすると、途中で解約せざるを得なくなり、かえって損をするケースもあります。
Q. どこまで削ったら“削りすぎ”になりますか?
「続けられるかどうか」が一つの目安です。
食費や娯楽費を削りすぎてストレスが溜まると、どこかで一気に爆発しやすくなります。
固定費など「一度見直せば、ずっと効果が続くところ」から整えていきましょう。
次の一歩に進みたい方へ
家計の土台が少し整ってきたら、「お金を増やす」「お金を活かす」も少しずつチェックしてみてください。