お金を増やす|つみたて投資・新NISA・金銀プラチナ・仮想通貨の“付き合い方”
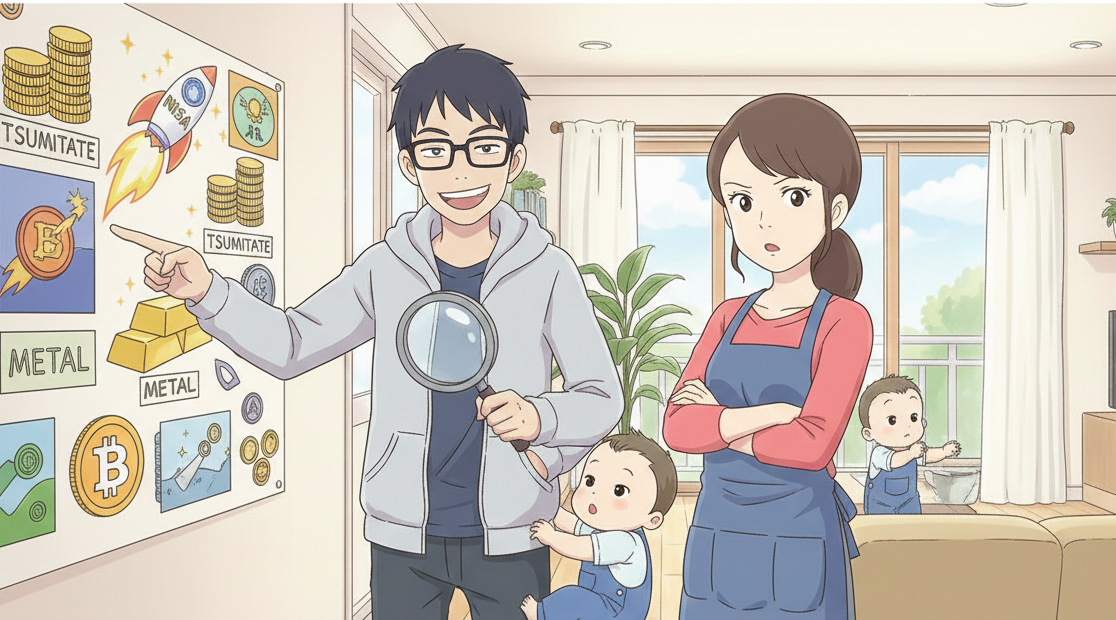
「貯金だけだと不安だけど、投資はこわい…」。
「お金を増やす」では、新NISAや投資信託といった王道のつみたて投資から、金・銀・プラチナなどの貴金属投資、仮想通貨まで、リスクとの付き合い方も含めて整理していきます。
「お金を増やす」で分かること
- 投資を始める前に決めておくべき「お金のルール」
- 新NISAや投資信託を使った、ムリのないつみたて投資の始め方
- 金・銀・プラチナなどの貴金属投資の特徴と注意点
- 仮想通貨投資のリスクと、付き合い方の基本スタンス
- 子どもの将来資金や老後資金を「時間を味方につけて」準備する方法
はじめに読んでほしい記事
投資が初めての方は、まず「全体像」と「王道のつみたて」から押さえるのがおすすめです。
投資を始める前に決めておきたい3つのこと|目的・期間・リスク許容度
「なんとなく増やしたい」ではなく、何のために・いつまでに・どれくらいのリスクなら許容できるかを、
ざっくり言語化するところからスタートします。
新NISAのキホン|子育て世帯が知っておきたいポイントだけ解説
制度の細かい話よりも、「結局どう使えばいいのか?」に絞って解説。
将来資金づくりの軸として、新NISAをどう位置づけるかを整理します。
月5,000円から始めるつみたて投資|家計にムリをかけないためのステップ
つみたて金額の決め方から、具体的な運用イメージまで。
「まずは小さく始めて、慣れてから増やす」スタンスで解説します。
お悩み別ガイド
あなたの「今の気持ち」に近いものを選ぶと、読み進めやすくなります。
💭 投資が初めてで、何から手をつければいいか分からない
- 投資初心者のための“むずかしい言葉を使わない”入門ガイド
- 投資を始める前に家計でチェックしておきたいポイント
- 少額から始める新NISAのステップ
😨 損をするのが怖くて一歩踏み出せない
- 暴落が起きたときどうする?「見ない勇気」とリスク管理
- 生活防衛資金を先に作るべき理由
- 「ハイリスク商品に全部突っ込まない」ためのルール作り
💰 金・銀・プラチナ・仮想通貨にも興味がある
- 金・銀・プラチナ投資の基本|株や投資信託とどう違う?
- 仮想通貨投資は「資産の一部」だけにとどめるべき理由
- 長期のつみたてと、値動きの激しい資産をどう組み合わせるか
テーマ別の記事一覧
新NISA・つみたて投資
- 新NISAのメリット・デメリット
- つみたて投資の始め方と注意点
- 教育資金・老後資金に新NISAをどう組み込むか
投資信託・インデックス投資
- 投資信託の基本と選び方
- インデックスファンドとアクティブファンドの違い
- 子育て世帯が選びやすい商品例
金・銀・プラチナなどの貴金属投資
- 金(ゴールド)投資の特徴とリスク
- 銀・プラチナ投資はどんな人に向いている?
- つみたて投資とのバランスの取り方
仮想通貨(暗号資産)投資
- 仮想通貨の基本と「投機」との違い
- 価格変動が激しい資産との付き合い方
- 家計全体から見た「どの程度までにしておくか」の目安
よくある質問
Q. 今から投資を始めても遅くないですか?
「早いに越したことはない」ですが、気づいた今からでも十分意味があります。
ただし、短期間で大きく増やそうとするほどリスクも大きくなるため、時間とリスクのバランスを取りながら計画を立てましょう。
Q. 金や仮想通貨に全部つぎ込んでもいいですか?
値動きが大きい資産に偏りすぎると、生活に支障をきたすリスクがあります。
まずは生活防衛資金を確保し、王道のつみたて投資を軸にしたうえで、
貴金属や仮想通貨は「資産の一部」にとどめるのが現実的です。
次の一歩に進みたい方へ
投資に踏み出す前後で、ほかのカテゴリもあわせてチェックしておくと安心です。